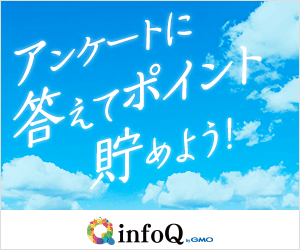-
すずめのせんこえつるのひとこえ
無能な人たちの多くの意見よりも
優秀な人の一言のほうが役立つという事。
また普通の人があれこれ話をするよりも
優れた人の言う言葉のほうが価値があるという事。
小さな雀がたくさん集まり鳴き声を上げるよりも
鶴が一声あげるほうがとても存在感があるという事から。
衆愚の諤々たるは一賢の唯々には如かず
禽鳥百を数うると雖も一鶴にしかず数星相連なると雖も一月に如かず
百星の明は一月の光に如かず
- 鶴の一声(つるのひとこえ)
多くの人たちが議論しても決まらなかった事を
有力者の一言であっさりと決定する事。
大きな発言力を持つ人の意見の事。
鶴は首が長く発声器官が発達しているため
大きな鳴き声を上げる事が出来、
その鳴き声は遠くまで力強く響くという事からそう呼ばれる。
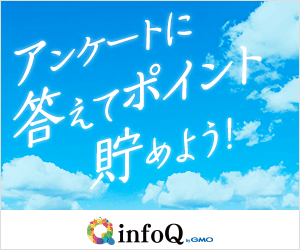

-
ずくひきがずくにひかれる
相手をひどい目にあわせようとして
逆に自分がひどい目にあってしまう事。
ミミズクは昼間目が見えない事を知っている鳥が
ミミズクをからかいに行ったところ
待ち伏せしていた猟師につかまってしまうという事から。
ミイラ取りがミイラになる
人とる亀が人にとらる
- 木菟引き(ずくひき)
ミミズクを紐で結びその周りに鳥もちの付いた細い棒を仕掛け
昼間目の見えないミミズクの周りに集まる小鳥を捕えようとする猟の事。
- 木菟(ずく・みみずく)
顔に耳のような羽毛の生えている鳥《ミミズク》の事。
木兎(みみずく・ぼくと)などとも書き
木の上にいる兎の意味と言われ
ミミズクの語源には《耳付く》から来ているという説もある。
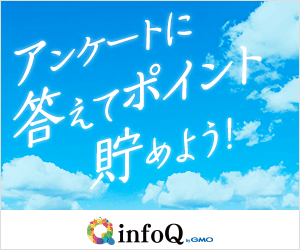

-
ずきんとみせてほおかむり
見た感じではよい状態で立派に見えるのだが
実際には余裕がなく不十分なものを補うので精一杯である事。
見せかけほどゆとりがない事。
頭巾とは頭にかぶる布を使用したかぶり物の事で
その頭巾に見た目は似ているが
手ぬぐいで頬冠をして頭巾の代用をしているという事から。
内は火が降る
内証は火の車
- 頭巾(ずきん)
かぶり物の一種で風雪などから頭や顔を守ったり
他人に人目をさらしたくないような場合に使用されるもの。
袋状などに初めから作られており頭にかぶる専用の布。
- 頬冠(ほおかむり)
頬被り・ほっかぶりなどとも呼ばれる。
頭や頬などに手ぬぐいや衣類などで覆い顎の下で結んだ状態の事。
手ぬぐいは手や顔などを拭くものでそれを日よけなどのため頭に巻いたもの。