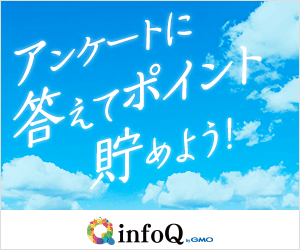-
さおさんねんにろはっちょう
一見すると同じように見えるものでも
本質の違いにより難しさが違うという事。
どちらもぱっと見は同じような長い棒ですが
棹は細長い竹の棒で川底を押すようにして進み
この方法で舟を直進させるのは難しく習得するのに三年かかるが
艪は途中からへの字のような形をしたオールのようなもので
これを左右に動かす事に少しひねりを加え
八の字を意識して動かすとよいとされ
八町ほどの距離を練習すると習得される事から。
櫓さんねんに櫂一とき
棹は三年艪は三月
- 八町(はっちょう)
一町とは約109mの距離となり
それが8倍の八町とは約872mとなります。
ちなみにですがオールを使用したボート競技では
通常1000mや2000mのコースを使用し
国際基準のレースでは2000mとなっていますが
国内では2000mの清水直線コースを確保するのが難しいので
1000mを使用しているとの事。

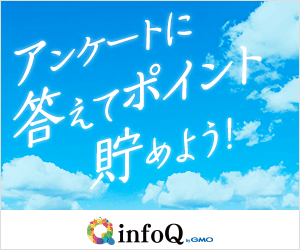

-
さいなんならたたみのうえでもしぬ
家の中にいれば安全であるというわけではない事。
どんな場所にいても災難というものは降りかかってくるものだという事。
確率は低いかもしれませんが
予期せぬ突然の巨大地震などで家が崩壊したり
突然ガス爆発のようなものに巻きこまれたりと
災難というものはどこでも起こりうるものであるという事。
- 畳の上で死ぬ(たたみのうえでしぬ)
年を取り家の中で天寿を全うする事。
事故や事件などのようなむごい死に方ではなく
病気や寿命などで家の中で死ぬ事。
事件性のない死。
昔は庶民の医者と言えば町医者で
入院設備などはなく診察や治療をしてもらう場所で
療養は自宅でしていたため、
亡くなるのは自宅の畳の上で
それが普通の死であった事から。