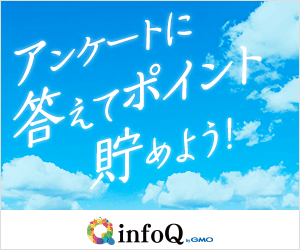-
ごこうよりだいざがたかくつく
人目につき目立つ表の部分よりも
基礎となる目立たない裏の部分のほうがお金がかかるという事。
仏像を作る時に後光の部分はとても神々しく目立つものですが
多くの人はあまりよく見る事はない仏像の土台となる台座に
多くの費用をかけないといけないという事から。
これは技術などでも同じで
基礎に多くのお金を投じその結果として革新的な技術が誕生するもので
基礎をないがしろにしてはよい技術など生まれないという事で
形だけ優秀な物を模倣し見栄え良くしても
基礎の技術にお金をかけていなければ長続きしないという事。
- 後光(ごこう)
仏や菩薩から出ていると言われる光の事。
またその光イメージした装飾を仏像などの背面に装着したもの。
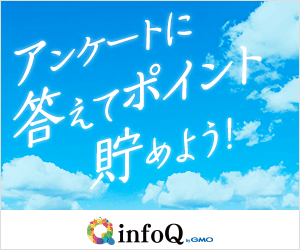

-
こけつにいらずんばこじをえず
悪い結果も考えられるような行動を行わなければ
大きな成功はしないという事。
リスクのある事を避けていては何も得る事はできないという事。
誰でもできるような事ばかりしていては
大きな手柄や大きな利益は望めないという事。
虎の住む穴に思い切って入るような冒険をしなければ
そこにいる虎の子供のような貴重な物は得られないという事から。
虎穴を探らずしていずくんぞ虎子を得ん
あぶない所に上らねば熟柿は食えぬ
高い所に上がらねば熟柿は食えぬ
うまい事は骨にある
- 虎穴(こけつ)
虎の住む洞穴の事。
そこからとても危険な場所の意味。
- 虎の子(とらのこ)
虎の子供の事。
また、虎の母性はとても強いため子供を宝のように育てる事から
大切な物や秘蔵の宝などの意味に使用される。
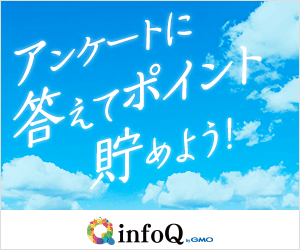

-
ごけそだちはさんびゃくやすい
厳しく躾けをする役割の父親が亡くなり
母親だけになった家庭の子供は甘やかされて育つという事。
これは母子家庭に限らず片親しかない家庭の子供に共通する事で
親が仕事に忙しく子供の相手をあまりしてあげる事ができない
という問題が関係しているもので
ダメな物はダメときちんと教えたりできない事からだと言われています。
現在はそうではありませんが本来善悪の区別というものは
父親が子供に教えるものという考えが昔はあったためであると思われます。
もちろん父子家庭・母子家庭のすべてがそうではないので注意が必要で
両親そろった家庭でも片親しか子供に接してない場合はそうなる事もあるそうです。
ばば育ちは銭が安い
- 後家(ごけ)
夫と死別した後、再婚をせず暮らす女性。
昔は未亡人という呼び名もありましたが現在では使用を控えているようです。
- 三百安い(さんびゃくやすい)
三百文は価値の低いものだったことから低級で価値の無いものという意味。

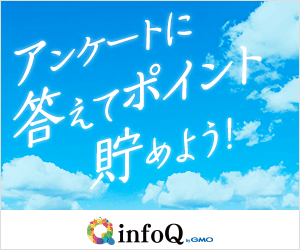

-
ごくらくねがわんよりじごくつくるな
死んだ後に極楽へ行けるように毎日神仏に祈るよりも
生きてる時に地獄へ落ちるような悪行を行わないよう心掛けよという事。
幸福を願うよりも
まずは不幸になるような行動を慎むべきだという事。
- 十悪(じゅうあく)
仏教では苦しみを生み出す悪果として十の悪があげられます。
①貪欲(とんよく)欲深い事。
②瞋恚(しんい)怒る事。
③愚痴(ぐち)言ってもしょうがない事を言う。
④綺語(きご)道理に合わない事を表面だけ飾る事。
⑤両舌(りょうぜつ)二枚舌の事。
⑥悪口(あっこう)言葉で他人の名誉を傷つける事。
⑦妄語(もうご)嘘を吐く事。
⑧殺生(せっしょう)むやみに生き物を殺す事。
⑨偸盗(ちゅうとう)盗みを働く事。
⑩邪淫(じゃいん)不倫や性犯罪など。
悪口などは言うと憂さ晴らしとなり気持ちが良いのでしょうが
実際には依存症のようになってしまうと脳にダメージがたまり
認知症のリスクや死亡率が上がるという研究もあるようで
まさに自業自得という事なのではないでしょうか。