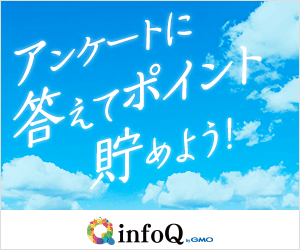"し"カテゴリーの記事一覧
-
しおからをくおうとてみずをのむ
事前の準備が良すぎるのも
時と場合により意味のないものだという事。
塩辛を食べるとのどが渇くからと言って
先に水を飲んでおいてもそれはあまり意味がないという事から。
例えば地震が来る前に倒れないよう家具の固定などは
事前に準備しておくのはよい事だが
火事になる前に家に水をかけておいても
家が湿気を帯びるだけでカビが生えるなどのマイナス面が多く
シチュエーションによって手回しの良すぎるのはどうかというもの。
塩辛食うとて水の飲み置きする
明日塩の辛い物食うからとて宵から水を飲んでも居られゃせぬ
夕立のせぬ先に下駄はいて歩かれるものかい
- 塩辛(しおから)
一般的にはイカで作った塩辛い発酵食品。
イカのほかにもタコやエビ・カツオやイワシなどで作られるものもある。
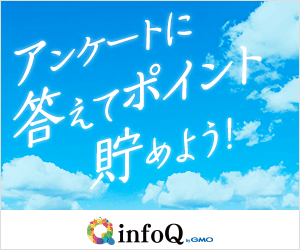

-
しあんのあんのじがひゃっかんする
安易な行動は慎むのが良いという事。
どんな事でも軽々しく行動を起こすのではなく
熟慮を重ねてから行うのが大事だという事。
思案という字は
このようにしたいという《思》と
予想や推量・考えなどを表す《案》からできており
行動を起こす前によく考え百貫の重さがあるように
軽々しく動く事なく決断するのが重要だという事。
堪忍の忍の字が百貫する
分別の別の字が百貫する
思案四百両
- 百貫(ひゃっかん)
一貫の重さが約3.75㎏なので百倍になると375㎏程となる。
またそこから非常に重い事の意味となる。
ちなみに百貫デブという言葉があるが
これは375㎏の太った人という意味ではなく
太って非常に重い人の意味である。
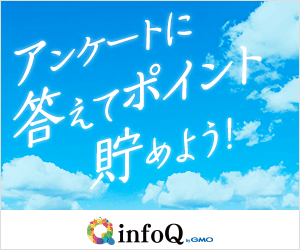

-
自慢高慢馬鹿の内
自慢の糞は犬も食わぬ
自慢は知恵の行きどまり
死命を制す
下いびりの上へつらい
下からは上がはかれぬ
四も五も喰わぬ
霜強ければ雨となる
霜の多い朝は晴
霜を履みて堅氷至る
麝あれば香し
蛇が蚊を呑んだよう
蛇が出そうで蚊も出ぬ
釈迦に経
釈迦に宗旨なし
釈迦に説法
杓子定規
杓子で腹を切る
杓子は耳搔きにならず
尺八は鳴りかけたら半稽古
邪慳な胸に鬼がすむ
麝香は臍故命をとらる
鯱鉾立も芸の中
尺蠖の屈めるは伸びんがため
借金は身上の薬
者と者の出合
蛇の口に蠅
蛇の道は蛇
蛇は寸にして人を呑む
しゃべる者は半人足
しゃべる者に知る者なし
沙弥から長老にはなれぬ
三味、太鼓の音の濁るのは雨の兆
十月の木葉髪
十月の投木
十月の昼間なし
習慣は第二の天性なり
十九立花二十は見花二十一では萎れ花
衆口は禍福の門
十三になる迄は七面変わる
宗旨の争い釈迦の恥
主と親には勝たれぬ
舅の物で相婿もてなす
姑が無事で嫁憎し
姑なければ村姑
姑に似た嫁
姑の敵を嫁が討つ
姑の気に入る嫁は世が早い
姑の十七見た者がない
姑の場塞がり
十人暮らしは暮せるが夫婦暮らしは暮せない
十人十色
十年一昔
重箱で味噌をする
重箱に鍋蓋
重箱に煮しめ
重箱の隅を楊枝でほじる
十分はこぼるる
十目の視る所十手の指す所
柔よく剛を制す
繻子の小袖に木綿裏
出家の念仏嫌い
出藍の誉れ
手套を脱す
朱に交われば赤くなる
蓴菜で鰻繋ぐ
駿馬痴漢を乗せて走る
上医は国を医す
将棋早馬碁は思案
しょう事無しの米の飯
上戸に餅下戸に酒
証拠の出し遅れ
上戸は毒を知らず下戸は薬を知らず
上戸めでたや丸裸
正直な者が馬鹿を見る
正直の頭に神宿る
正直の儲けは身につく
正直は阿呆の異名
正直は一生の宝
正直貧乏横着栄耀
障子口から上がれば坊主
小事と大事は一目には見難し
小事は大事
小人の腹は満ち易し
小心者は損をする
上手な嘘より下手な実意
上手の小糸
上手の鷹が爪隠す
上手の手から水が漏る
上手の猫が爪を隠す
上手はあれど名人はなし
上手は下手の手本下手は上手の手本
冗談から泣きが出る
上知と下愚は移らず
小智は菩提の妨げ
笑中に刀あり
少年老い易く学成り難し
少年よ大志を抱け
小の虫を殺して大の虫を助ける
商売は草の種
商売は道によりて賢し
商売は元値にあり
勝負は時の運
正法に奇特なし
証文が物を言う
証文の出し遅れ
醤油で煮締めたよう
小利大損
将を射んとせば馬を射よ
小を捨てて大につく
升を以て石を量る
諸行無常
食後の一睡万病円
食なき者は職を選ばず
職人貧乏人宝
女子と小人は養い難し
初心忘るべからず
白髪は冥途の使い
白河夜船
知らずは半分値
知らずは人に問え
白豆腐の拍子木
知らぬ顔の半兵衛
知らぬが秘密
知らぬが仏
知らぬが仏見ぬが秘事
知らぬ神より馴染の鬼
知らぬは亭主ばかりなり
知らぬは人の心
知らぬ仏より馴染の鬼
知らぬ道も銭が教える
白羽が立つ
虱の皮を槍で剥ぐ
虱は頭に処りて黒し
尻あぶって百まで
尻が来る
尻から抜ける
尻が割れる
知りて知らざれ
尻に帆かける
尻に目薬
尻は他人
尻も結ばぬ糸
知る人は国に余れ
知る者は言わず言う者は知らず
汁を吸うても同罪
次郎にも太郎にも足りぬ
白無垢鉄火
師走女房に難つけな
師走八日に事なかれ
しわん坊と灰吹は溜る程汚い
しわん坊の柿の種
詩を作るより田を作れ
人口に膾炙す
沈香も焚かず屁もひらず
心中よりも饅頭
人事を尽くして天命を待つ
信心すぎて極楽通り越す
信心は徳の余り
人生字を識るは憂患の始
人生朝露の如し
人生僅か五十年
身代につるる心
死んだ子に阿呆はない
死んだ子の年を数える
死んだ先を見た者いない
死んだ仏も盆にゃ来る
死んだ者の因果
死んだら褒められる
死んで千杯より生前の一杯
死んで花実が咲くものか
死んでも書いた物が物を言う
真の闇より無闇が怖い
心配は身の毒
親は媒に因らず
親は泣き寄り他人は食い寄り
心腹の友
辛抱は金、碾臼は石
新米にとろろ汁

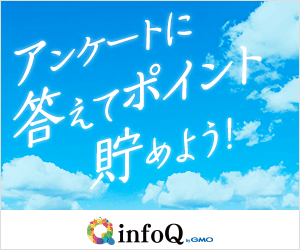

-
仕上げが肝心
仕合せは袖褄に付かず
思案投げ首
思案の案の字が百貫する
しいら者の先走り
塩辛を食おうとて水を飲む
塩を売っても手を嘗める
塩を売れば手が辛くなる
仕返しは三層倍
四角な座敷を丸く掃く
四月雷さま馬鍬吊るす
鹿待つところの狸
鹿を追う者は山を見ず
鹿を指して馬となす
閾が鴨居
閾を跨げば七人の敵あり
食には友を忘る
しくじるは稽古の為
自業自得
地獄極楽は心にあり
地獄で仏に逢ったよう
地獄にも知る人
地獄の釜の蓋もあく
地獄の沙汰も金次第
地獄は壁一重
地獄へも連れ
地獄も住家
仕事は多勢
仕事幽霊飯弁慶
仕事に追うて仕事に追われるな
しし食った報い
獅子身中の虫
事実は小説より奇なり
死しての千年より生きての一日
獅子の子落とし
獅子の分け前
獅子は小虫を食わんとしてもまず勢いをなす
蜆貝で海を量る
磁石鉄を吸うとも石を吸わず
磁石に針
四十肩に五十腕
四十がったり
四十くらがり
四十過ぎての道楽と七つ下がって降る雨は止みそうでやまぬ
四十二の二つ子
支証の出し遅れ
師匠のはな負け
師匠は針の如し
地震雷火事親爺
地震のある前には魚類が多く浮き上がる
地震の時は竹藪へ逃げろ
賤に恋なし
死すべき時に死せざれば死にまさる恥あり
沈む瀬あれば浮かぶ瀬あり
死生命あり
時節の梅花春風を待たず
時期を待てよ柿の種
自然に還れ
地蔵の顔も三度
地蔵は言わぬがわれ言うな
士族の商法
舌三寸に胸三寸
親しき中に垣をせよ
親しき中にも礼儀あり
下地は好きなり御意はよし
舌の剣は命を絶つ
舌の長い者は盗人
舌の根の乾かぬうち
舌は禍の根
七去
七細工八貧乏
七尺去って師の影を踏まず
七十の三つ子
七度探して人を疑え
七人の子はなすとも女に心は許すな
死中に活を求む
七里けっぱい
知った同士はすずしい
知った道に迷う
知って知らざれ
知って問うは礼なり
実は嘘の奥にあり
十遍探して人を疑え
十本の指はどれを噛んでも痛い
師弟は三世
地頭に法なし
四斗を八斗
死なぬ子三人皆孝行
死なば四八月
死なば卒中
死馬に鍼さす
死馬にも鍼
死にがけの念仏
死金を使う
死にし子顔よかりき
死に別れより生き別れ
死人に口なし
死人に妄語
死ぬ死ぬという者に死んだ例がない
死ぬ程楽はない
死ぬ者貧乏
死ぬる子は眉目よし
死ぬるばかりは真
死ねば死損生くれば生得
芝居蒟蒻芋南瓜
芝居好きは女好き
芝居は無筆の早学問
四百四病の外
四百四病より貧の苦しみ
渋柿が熟柿に成り上がる
渋柿の長持ち
持仏堂と姑は置き場なし
自分で自分の墓を掘る
自分の子には目口が明かぬ
自分のぼんのくぼは見えず
耳聞は目見に如かず